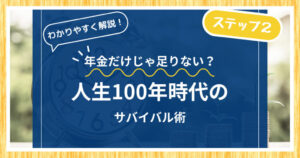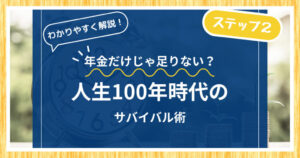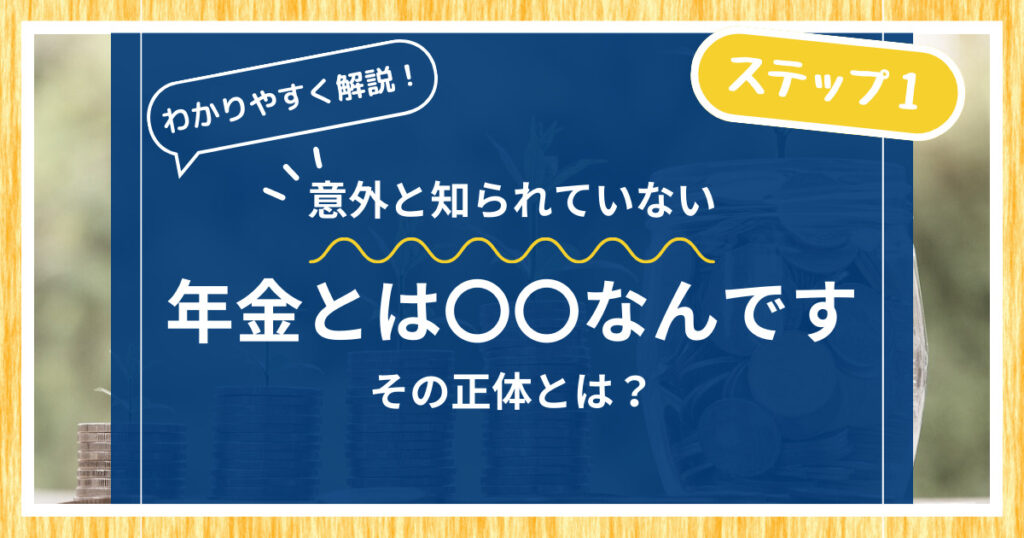「年金」って言葉は知っているけど、実はその中身は良く知らない・・・。
こんな方も多いのではないでしょうか?
「老後に2000万円必要なの?」
「そもそも将来年金ってもらえるの?」
「年金の種類が多くてわけわからん!」
を、ゼロから子供でもわかるように解説します。
今流行りのiDecoやNISA。実は年金との関係性がとても深いのです。
この記事で年金を正しく理解し、将来のお金の不安を払しょくして人生を楽しみましょう。
【老後2000万円問題】えっ!老後に2000万円も必要なの?
みなさんも聞いたことがあると思いますが、過去に「老後2000万円問題」という言葉が世間を騒がせました。
老後に2000万円も必要だということで、「そんなに貯められるわけないだろ!」ということで大問題になったのです。
実はこの「老後2000万円問題」を理解できると年金というものが理解できるのです。
それでは見て行きましょう!
老後2000万円不足問題は解決されたのか?
「老後2000万円不足問題」が社会的に大きな反響を呼びましたが、その後、国民が十分に納得し、不安が解消されたわけではありません。
多くの人々は依然として「いつか2000万円を貯められるだろうか」と漠然と考えたり、あるいは現実的でない解決策にすがろうとしたりしています。
しかし、本来必要なのは恐怖や不安をあおられることではなく、その仕組みや背景を正しく理解することです。
理解が深まれば、漠然とした不安に振り回されるのではなく、具体的な対策を立てるという前向きな行動に変えることができます。いわゆる
「適切に恐れる」「適切に心配する」
という状態に近づけるのです。逆に、理解が不十分なままでは「理由はわからないが何となく怖い」という不安だけが残り、かえって大きな心理的負担となります。
この先に示す説明を通じて、そのような漠然とした不安から脱却できるようになるはずです。
年金という仕組みは、多くの人にとって「まだ先の話」という印象を与えがちです。
しかし、現実には若い世代にとっても大きな関心事となっており、心の負担にもつながっています。
実際、「老後2000万円不足問題」の際にデモ活動を主導したのは20代から30代の若者が多く、年金制度に対して不平等感や不公平感、さらには不信感を強く抱いているのが現代の若者世代であるといえます。
老後2000万円問題はなぜ炎上したのか?
2019年6月3日、金融庁が「公的年金だけでは老後に2000万円不足する」という報告書を提出しました。
つまり「年金をもらっていても2000万円も足りなくなりますよ~」という、とてつもなくインパクトのある言葉でした。
我々は将来不足しないように願いを込めながら年金を納めている。それなのに不足すると言われ
「どういうことなんだ!!」
と炎上してしまいました。
日比谷公園でのデモ活動
2019年6月18日、日比谷公園で「年金でちゃんと俺たちを助けろよ~!」、「なんのために国民は年金を納めているんだ!」とデモ行進が行われました。
政府の対応とこの問題の末路
当時金融相の麻生大臣は「その報告書は受け取らない」という謎の行動に出ました(笑)
結局、公的見解はどうなのか、足りるのか?、足りないのか?の議論があまりされることはなく、時間の経過と共に、ワイドショーからもこの話題が過ぎ去っていきました。
2000万円の根拠
では、「公的年金だけでは2000万円不足する」というデータはいったいどういう根拠だった?
ここもパッとわかっていない方が多いと思います。
これを説明すると、ここのデータ自体がかなり雑だというのがすぐにわかるのです。
高齢夫婦無職世帯の平均値
平均収入 – 平均支出 = – 5.5万円(毎月)
毎月収支 5.5万円赤字 x 30年(65歳~69歳)=約2,000万円
このようにかなり大雑把な数字なのです。なぜ大雑把かというと、平均値で算出してしまっているのです。
普通は自分の収入と支出ってなんとなく帳尻合わせますよね。月30万円稼いでいる人が月300万円使うことってあまりありませんよね。
この「平均値」を取ったということが、どういうことかと言うと、非常に高収入なたくさんの支出を出している人と、とても少ない収入の中で支出を抑えているって人が一緒にされているということなのです。
例えば、あるお店があり、そこにはお客さんが2人います。
客A 5000円の支払い
客B 100万円の支払い
そうすると、そのお店でのお支払を平均すると約50万円という数字が出てきてしまうのです。
従って、平均値を出すのはかなり雑なのです。
金融庁は、なぜ雑な報告をしたのか?
金融庁はある目的をもってデータを発表しました。これは「気を付けてくださいね」という国民への警鐘ではありませんでした。金融庁が本当にしたかったこと、それは、、、
銀行・証券業の活性化のため「投資の必要性」を訴えたかった
「皆さん、投資とか資産形成やっていますか?やらないと老後ちょっと不安かもしれませんよ~」
という、通常ならば銀行や証券会社の窓口で営業マンがセールストークとして言うようなセリフを、金融庁が大々的に発表してしまったことで国民の不安を一気に爆発させてしまった、
ようするに「セールストークがスベって暴動」が起きてしまった。というPRミスだったのです。
本来であれば投資する余力のある人が、
「それならば老後までに投資で2000万円作るぞ~!」
となり、貯蓄だけではなく、投資にもお金をまわしてもらい、その結果金融業界が活性化され、日本人の資産形成への意識も高まる。
という構図を期待していたのですが、2000万円近く持っている投資に余裕のある中高年にはまったく響かずに、
「2000円持ってないし、稼げる自身もない・・・」という、年金に対して不信感のある若年層を刺激してしまったのです。
将来、年金はもらえるのか?
こんな話を聞いたことありませんか?
「年金っていずれもらえなくなるよ」
「少子高齢化で多くの老人を背負わされている」
「自分たちが大人になるころには年金の仕組みは破綻してるよ」
実はこれ、解決済みの議論だったのです。知ってましたか?
実は解決済みの議論だった
政府は2004年から、少子高齢化のアンバランスさを是正する仕組みを取っているんです。
それは「マクロ経済スライド」と呼ばれる調整システムで、物価や賃金の動きに合わせて年金も変動(上げ下げ)する仕組みです。
物価がものすごい勢いで上昇しているのに年金が一定だったら年金暮らしの人たちが貧しくなりますよね。だから物価が上がれば年金も上がるという調整をするのです。
ただ、上げすぎると不平等がおきるので、上げた一定額を後の世代にスライドする(残しておく)、ということを理論をはじき出しながら少しずつ実施されていますので「大丈夫だよ」という議論も行われているんです。
でもそんなことは我々には届いていませんよね。なぜこのような議論がなかなか進まないのか、それは政府が、年金という仕組みを根本からしっかりと国民に伝えていないからなんです。
これまでも「年金未納問題」などの問題があり、
「未納が多いからもうダメだ。お金がない!」
と騒がれましたが、それは間違いです。
未納が多い人には払われないだけなんです。あまり影響はないんです。
未納だと騒がれていたのは国民年金の一部で、厚生年金は大丈夫でした。
年金の種類(公的年金、私的年金)
先ほど「国民年金」、「厚生年金」と言いましたが「あれ、何だっけ?」ここですよね。
国民年金と厚生年金、この2つを「公的年金」といいますが、「公的でない年金もあるんですか?」
はい、あるんですよ。
私的年金といって、「国民年金基金」「確定拠出年金」「iDeco(イデコ)」、、、
「え~わからない、パニック、吐きそう(笑)」こうなってしまいますよね。
だからみんな「うわぁぁ」ってなって、「勉強したくない~!」となるのですが、
今回それを「ギュッと」凝縮します。
この問題、つまり「年金って何なの?」が国民にわかられていないまま時代が進んでいることが問題なのです。
老後2000万円不足問題は、年金について理解していない人達を刺激してしまった。
でも今みなさんは、先ほどの説明で
「なるほど、金融庁がそうPRしたかったのね」と理解したと思います。
でもその問題の根本にある「年金ってなんなの?」が、まだわかっていないからこその不安。
これを治療しないと根本の治療にはならないですよね。
それをこれから治療したいと思います!
概要だけ覚えれば大丈夫!
年金には「公的年金」と「私的年金」と2種類あります。
公的年金: 国民年金、厚生年金
私的年金; 年金基金、企業年金、iDeCoなど
この「私的年金」がいっぱいあるんです!
今回覚えなくて大丈夫です。リラックス、深呼吸してリラックスしてください。
とりあえず、考えるきっかけだけ、概要だけわかっていただければいいです。細かいパーセンテージとか金額とか覚えなくていいです。
覚えていただきたいのは、今回この「公的年金」というのが(2000万円問題などの)話題になっていて、これが土台となる年金なんです。
「国民年金」とは会社員も自営業も入れる。
「厚生年金」は会社員のみ
だから「自営業の人はもらえる額が少ない」、「会社員の方が多く納めているから多くもらえる」と、何となく聞いたことあるのではないでしょうか。
まずはこの2つで十分です。
その上で、この2つ、国民年金と厚生年金だけでは足りないよという議論があるわけなんです。
もっと老後に必要だという方のために私的年金と呼ばれる年金基金、企業年金、iDeCoがありますが、ここはあくまでも「プラス・α(アルファ)」のお話。
年金と言ったら「国民年金」「厚生年金」のことなんです。この、「公的年金とは何なのか!?」
この根本の理解ができたらかなりスッキリします。
すべての根源「そもそも年金は何なのか?」「何に近いのか?」
少し考えてみてください。年金は何に近いと思いますか?すべてはこの一問だけで終わります。
年金はどれに近い「積立貯蓄」「生活保護」「保険」?
ご友人、ご家族に聞いてみてください。
年金って貯金みたいなもの?
生活保護みたいなもの?
保険みたいなもの?
この3択でだいぶ年金への理解が上がります。
みなさん、「なんか積み立てたら最後もらえる貯金みたいなもの」だって思っていませんか?
「積み立てろって言われたから積み立てたのに、それがもらえないっていうんだったら腹が立つ」っていう状態ですよね。でも、
年金は積立貯蓄とは違います。
では生活保護みたいなもの?
確かに、老後の人たちはお金持ちばかりではありません。貯金がある人もいれば、無い人もいる。
「お金が無い人を助ける。それが年金だ!」
そうお考えの方もいると思いますが、それも違います。
もっとも近いのは自動車事故のために入る保険がありますよね。その「保険」に近いのです。
年金は保険に近い
自動車保険は、自動車で事故があるかもしれないというリスクに備えて、みんなで少しずつお金を出し合って、そしてそのリスクを請け負ってしまった人に支払う仕組みですよね。
言わば、「共同でのリスクヘッジ(起こりうる危険に備えること)ですよね。」
自動車保険に入っていて、事故は起こらなかった。それに対して、
「おい、もらえてないじゃないか。おれ無事故で天国行った。自動車保険どうなった!」
と言う人はあまりいませんよね。みんな「事故が無くて良かった~」って思いますよね。
実はそれが「年金」なんです。
ではリスクとはなんでしょうか?それは、長生きするリスクなのです。
日本人の女性であれば80歳後半、男性であれば80歳前半など、「平均寿命」ってありますよね。
でもこれって「平均」なんですよね。これは幼少の頃に亡くなってしまった方も含まれているのです。
したがって、60歳以上の人たちは平均寿命の80歳を超える可能性が高い。
80歳まで生きる想定でお金を備えていたけど、長生きして95歳になった時に「もうお金ありません!」となるのが「長生きしてしまうリスク」なんです。
人は、「長生き=ラッキー」なため、リスクをなかなか理解できないんですね。
経済的な予測が立てずらくなって生活費をどう準備していいかわからなくなる。これを「リスク」としてとらえた場合の「保険」なんです。
年金は長生きリスクに対する「保険」
積立貯蓄 → 自助 → 自分で貯めたものを自分で使う
生活保護 → 公助(救貧) → 貧しくて生活できない人を救う福祉的な考え方
保険 → 共助(防貧) → 貧しくなるのをみんなで協力して防ぐ
これが年金の考え方なのです。
実際に年金って足りるの?足りないの?
これは、自営業か会社員か、家族の有無や子供の有無、都市部に住んでいるかいなかいか、税金も違えば給与も違う、納めている年数も違うため、一概に言えないんです。
一人一人に話を聞いて「将来的な状況も加味して・・・」と言わなければならず、だから難しいのです。
したがって、足りるか、足らないかは個人次第なんです。
でも大事なのは、2つあります。
- 年金は「長生きリスクに対する保険」だということを理解すること
- 将来的に今どういう準備が必要か?をわかっておくこと
足りるようにする方法論は次回のブログでお話しします。
まとめ
いかがでしたか?年金とは長生きリスクに対する「保険」という位置づけなんですね。
「なるほど!」って感じですよね。
老後2000万円問題は金融庁のPRミスであり、必ずしも全員が2000万円必要とは言い切れないということでした。
皆さんは将来のお金、足りそうですか?
次は人生100年時代の生き方と、賢い年金の受取り方について教えてくれます。
それでは続きをご覧ください。